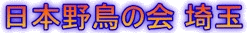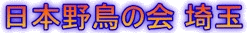| 4/9/’25 さいたま市・田島ヶ原サクラソウ自生地植物観察会 |
| 報告: 野津 弘毅 |
| さいたま市の桜草公園内にある田島ヶ原サクラソウ自生地は、日本で最初に指定された天然記念物の一つで、約4.1ヘクタールの土地にサクラソウをはじめ希少種を含む約250種の植物が自生しています。実は私はここ数年、この時期に毎年1回はここを訪れサクラソウを観賞していますが、一人で行っていては知ることが覚束ない、サクラソウ以外の希少な植物についても知りたいと思っていました。そこで今回この日本野鳥の会埼玉の探鳥会ならぬ植物観察会に参加した次第です。ちなみに田島ヶ原サクラソウ自生地は「サクラソウ」自生地なのですが、自生地の大半を埋め尽くすのはやはり希少種のノウルシで、サクラソウは自生地の中にポツッポツッと咲いている感じです。 |

田島ヶ原サクラソウ自生地全景 |

ノウルシ |
出発前にリーダーより、田島ヶ原サクラソウ自生地は、大正9年(1920年)に日本で最初に指定された天然記念物で、昭和27年(1952年)には天然記念物の中でも特に重要なものとして特別天然記念物に指定されたと説明がありました。そして特に観察してほしい希少種の花のある植物、花のない植物、計53種のリストが配付されました。
出発直後はまず黄色いカントウタンポポの中に少数咲いているシロバナタンポポなどを観察し、ヨシとオギの識別について教わりました。私は特にスイバの名前を教えて頂きました。 |

リーダーによる出発前説明 |

シロバナタンポポ |

ヨシ |

オギ |

スイバ |

観察会を通じてよく見たベニシジミ |
| そしていよいよサクラソウ。準絶滅危惧種の可憐な花をしばし観察します。出発前に頂いたさいたま市教育委員会発行のパンフレットによると、サクラソウは毎年2月頃地上に芽を出し、花は4月上旬に見ごろを迎え、その後はヨシやオギが強い日差しから地下茎と根だけになったサクラソウを守り、人の手による刈払いや草焼きも行われ、自然と人の関わりがサクラソウの良い環境を維持しているそうです。 |

サクラソウ観察の様子 |

サクラソウ |
| この日、サクラソウより主役だったのは、リストアップされた計53種の中でも特に希少だとリーダーからアドバイスのあった3種の植物。トダスゲ、ヒキノカサ、ゴマノハグサです。正直、トダスゲとゴマノハグサは、そう言われても地味な植物でしたが、ヒキノカサの水で濡れたような花の”艶"には惹きつけられました。ただ私の腕では写真でそこまで表現できなかったのは残念です。 |

自生地の中の通路を行く |

ヒキノカサ |

トダスゲ |

ゴマノハグサ |
| 植物観察会だったのですが野鳥も見ました。公園南東を流れる鴨川にはヨシガモがいて、結構皆さん、一生懸命見ていました。その他、マガモ、オオバン、コサギもいました。振り返るとツグミが数羽、地面から木の枝に飛び移ったりしてもいました。 |

鴨川の野鳥を観察 |

ヨシガモ |
| 観察会最終盤のハイライトはシロバナサクラソウとオドリコソウです。自生地全体でほんの数輪しか咲いていない”白い”サクラソウは、観察会でなければ気が付かなかったでしょう。オドリコソウはリストにありませんでしたが、この花も特に希少な花だとリーダーから説明がありました。実際写真の花しか咲いていませんでした。貴重な経験です。ちなみにわりとよく見るヒメオドリコソウは外来種だと説明もありました。オドリコソウの傍らで、倒木なのに花をつけたソメイヨシノを見て生命の力強さを感じました。 |

シロバナサクラソウ |

オドリコソウの観察に向かう参加者 |

オドリコソウ |

倒木なのに花をつけたソメイヨシノ |
自生地をひととおり周って集合場所の桜草公園管理棟まで戻ってきて植物観察会も終了です。終了直前に観察したチガヤについてリーダーより、オオヨシキリがよく巣材に使う植物だ、と説明がありました。鳥合わせ的なものもありませんでしたが、一旦散会した後、希望者のみ”自生地”ではない公園入口の土手などを観察するおまけ観察会もありました。ここでもそこ一箇所にしか生えていなかったであろう、シロバナホトケノザなど観察しました。さらに上空を飛ぶイワツバメも見ました。
この植物観察会に参加しなかったら一生見なかった、あるいは気が付かなかった植物に触れ、非常に勉強になった1日でした。リーダーの皆さん、参加の皆さん、有難うございました。
|

チガヤ |

集合場所に戻って解散 |

公園入口の土手の植物を観察 |

シロバナホトケノザ |